DXとIoTの違いは?その関係や導入する際のポイントを解説
DX
2023.09.01
2023.09.01

DX=IoTという偏った認識を持っている人も多いようですが、本来はDXとIoTとは異なります。モノのインターネット化を意味するのがloTで、デジタル技術を用いてビジネス・日常生活の質向上を目指すのがDXです。本記事では、DXとIoTの概念的違いやDX化によるメリット、DX化の方法を詳しく解説します。
DXとは
DXとは、デジタルトランスフォーメーションの略で、進化し続けるテクノロジー(IT技術)を活用して、生活をよりよいものに変化させていく概念のことを指します。
2018年に経済産業省が発表した「DXレポート」「DX推進ガイドライン」では、DXを次のように定義しております。
「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」
引用元:DX推進ガイドライン(経済産業省)
デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会を行ったり、DXのレポートを発表したり、国がDXを推奨しております。
IoTとは
IoTは"Internet of Things"の略で、日本語では"モノのインターネット"と直訳をすることができます。 言葉通り、ありとあらゆるモノをインターネットで繋ぎ、スムーズに情報をやりとりできる仕組みのことを意味します。
モノのインターネットと聞いて、具体的なイメージを持つことを難しいかもしれませんが、私たちの生活になじみ深いIoTデバイスとしては、スマートスピーカーがあげられます。
loT技術を使い、声の指示によるデバイスの遠隔操作を可能としている例です。
私たちの生活になじみ深いIoTデバイスとしては、スマートスピーカーがあります。loT技術を使い、声の指示によるデバイスの遠隔操作を可能としている例です。
IoTとユビキタスの関係とは
ユビキタスとは、コンピューターやネットワークが日常の生活に一般的になることを指します。
コンピューターやネットワークの普及が2000年前後に、日本は「ユビキタスネットワーク」という言葉が浸透されました。2010年からは、スマートスピーカーなどIoTを使用した電化製品が普及されはじめ、「ユビキタス」の概念が「IoT」によって実現が可能になりました。
DXとIoTの違いとは
DXとIoTについてここでは説明をしてきました。 IoTと同様に、ICTもDXと混同されてしまいがちです。 ここでは、DXとICTの違いについて説明いたします。
IoTとDXの違いは「モノ」と「コト」の違い
DXとは先に述べたように、モノ同士のつながりだけではなく、ビジネスでいえば「サービス全体をデザインしよう」という意識です。
一方、DXはデジタル技術を用いてビジネス・日常生活をより良くしようという心がけのことを指します。モノ同士のつながりだけではなく、ビジネスでいえば「サービス全体をデザインしよう」という意識がDXです。つまり、"構造としてはDX化のツールとしてIoT技術を活用している"というかたちになります。
「生活=コト」の変化を目指すDXの中に「デバイス=モノ」を変化させるIoT技術がある、と認識しておくとよいでしょう。
DXとICTの違いとは
DXとIoTについてここでは説明をしてきました。IoTと同様に、ICTもDXと混同されてしまいがちです。ここでは、DXとICTの違いについて説明いたします。
ICTとは
ICTとは"Information and Communication Technology"の略で、"情報伝達技術"と日本語訳をすることができます。ITと大きな意味合いで違いはないですが、ITよりもICTの方がコミュニケーションの意味が強くなります。
「ICT」は、AIやIoT、5Gなどのインターネット(IT)の技術にコミュニケーション機能を加え、利便性を高め業務効率化や人手不足の解消などに役立つ機能のことで、普段何気なく過ごしている中でもたくさんICT機能に触れております。例えば、eラーニングやWeb会議などがあげられます。 先ほど説明したIoTもICTに内包されていることがみなすことができます。
ICTとDXの違いは利用する場面が違う
ICTとDXは、ITを活用するという点で同じです。
ただ、ICTと同じようにIoTもDXの中に内包されます。つまり、DXはIOTやICTの技術を利用して、生活を豊かにすることを指します。
IoTを活用したDX化によって可能になることは5つ
IoTを活用したDX化によって可能になることは、以下の5つです。
1. アナログでおこなっていた業務を効率化できる
IoT技術を用いてDX化を推進すると、業務を効率化できます。アナログでおこなっていた業務上の情報伝達などを、IoT技術によって効率化できるからです。たとえば工場のDX化においては、製造ラインで不良品を検知して改善するIoTシステムを組み込むことができます。かつてアナログでおこなっていた業務は、DX化によって全て自動化できるので生産効率が上がります。
2. 膨大なデータベースを用いて組織化できる
DX化を進めると、膨大なデータベースから作業を区分して、社内部署に適切に割り振ることが可能です。さらに、適切な部署を設置して正しく組織化しやすくなります。
3. 業務フローを見直し最適化できる
DX化の導入によって、業務フローの中で自動化できる部分はシステムを構築し、最適化することが可能です。無駄なシステムと時間のコストを削減でき、従業員を雇う必要がなくなります。その分のコストも抑えられるでしょう。
4. 働きやすい環境を提供できる
DX化によって作業を自動化したり、パソコンのみで作業を終えられる状態にできれば、従業員にとって「働きやすい環境」を実現することが可能です。
負担を減らせることから従業員の満足度が上がり、会社に貢献しようという意識が芽生える可能性がありますし、働き方改革の促進にもつながります。
5. データを基に商品・サービスの開発がしやすくなる
DX化によってビッグデータを収集しやすくなっているので、顧客ニーズに沿ったリアルな分析が可能となります。
また、IoTによるDX化を促進することで、時間を有効活用できます。今までアナログでおこなっていた管理の人員を商品・サービス開発部署に総動員できるので、より開発に専念することができるでしょう。DX化は上記2つの意味で商品・サービス開発の効率が上がり、スムーズに進められるようになります。
IoTを活用したDX化を進めるためのポイントは5つ
IoTを活用したDX化を進めるためにはどのような工夫をすれば良いのでしょうか?ここでは、5つのポイントを紹介します。
1. 3〜5年先を見据えてDX化計画を構築する
まずは、3〜5年先を見据えてDX化計画を構築することが大切です。なぜなら、DX化計画には時間がかかり、実際の成果を出すまでに3〜5年ほど必要と言われているからです。つまり、直近の1年後程度を想定したDX化を進めたとしても、あまり意味のないものになってしまうかもしれません。
3〜5年後に重視されているビジネスはどのようなものなのか、自社がどのように成長していくのかを想像しながら、DX化の計画を構築することが大切です。
2. 既存のシステムを撤廃する
DX化に時間がかかる原因の1つに、既存のシステムを移動できないということが挙げられます。特に、既存システム内に膨大なデータが含まれている場合、新規システムに移行することは必須です。しかし、既存システムの精度によっては難しいこともあるでしょう。
社内メンバーで既存システムを移動できないのなら、信頼できる外注パートナーを雇ってDX化を効率化させるのも1つの方法です。いち早く既存システムを撤廃し、新しいシステムに移行するためにどのような工夫が必要かを考えましょう。
3. DX化推進能力があるIT人材を雇う
DX化を進めるためにはAIの知識やビッグデータの解析などを活用して導入できるエンジニアが必要になります。しかし、社内でDX化を進められる人材がいるケースはそう多くないはずです。
将来的にはDX化を効率よく進めていくため、社員全体がDX化の意識をもつ必要がありますが、最初はDX化のリーダーを雇うという方法が最も良い方法でしょう。
ただし、DX化を進める人材は非常に貴重なため、なかなか優秀な人材は見つからない可能性もあります。採用広報や採用メディアを活用して、採用を活発化させることも求められるでしょう。
4. DX化にふさわしいシステムを導入する
DX化のシステム選びも非常に重要です。DX化に用いるシステムが3〜5年後に後進的なものになってしまうようなものだと、DX化を導入する意味が薄れてしまいます。
また、どれだけ先進的なシステムを使っていても、自社にマッチしないシステムだったり、従業員が使いづらいと感じるシステムを導入してしまうとDX化をスムーズに進めることはできません。
まずは導入を検討しているシステムの利点を把握し、社内にぴったりマッチするものを選びましょう。DX化のシステム選びは慎重に行う必要があります。
5. 保守的な予算運用は避ける
IoTによるDX化には巨額の費用がかかります。DX化の理解が浅い経営者が中途半端な投資をおこなうと、多くの費用を無駄にしてしまう可能性もあるでしょう。
DX化には、ある程度の思い切りが大切です。もちろん無駄なシステム構築に費用をかける必要はありませんが、「必要な部分にはしっかり費用をかける」という意識を持ち、DX化を進めていきましょう。
経営者やトップ層の意見が食い違うと、適正な予算を設定できないケースがあります。予算の運用に関する共通の認識を持つよう、事前に情報を共有しておくことが大切です。
自社のコストやシステムを見直して、IoTを活用したDX化を進めよう
本記事では、IoTを用いたDX化について紹介してきました。DX化を推進させるツールとしてIoT技術があります。DX化を進めるためにはIoTの知識も必要になるということです。自社でDX化を実現できないようであれば、DX化に知見のある社員を雇うことも考慮しなければなりません。
DX化には巨額の費用と、3〜5年という時間的コストがかかってしまいますが、適切にDX化を実現することで業務効率化や収益UPに役立ちます。事業全体の質を上げることにもつながるでしょう。まずは、自社のDX化に何が必要かを把握するところからはじめてみましょう。







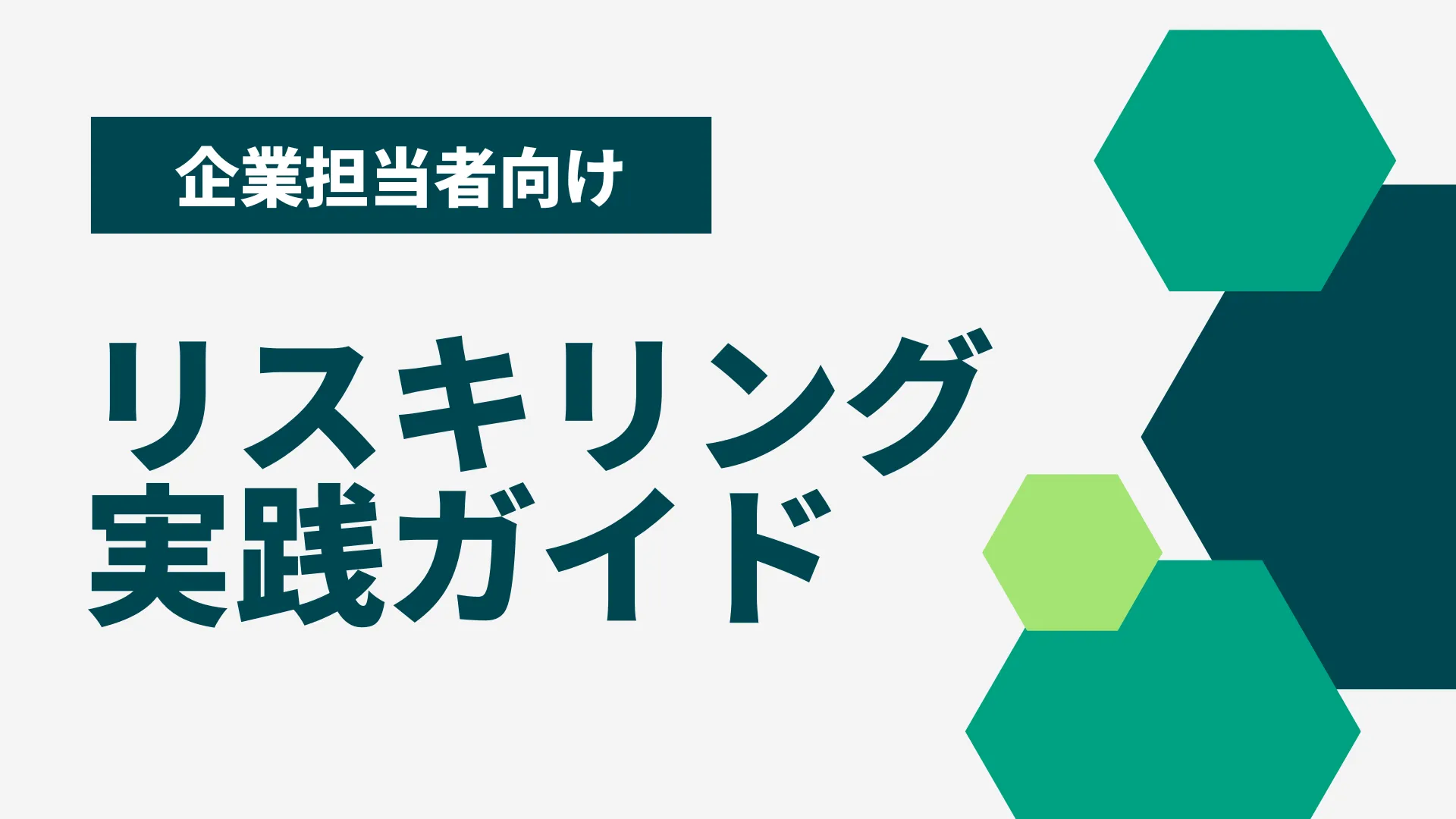






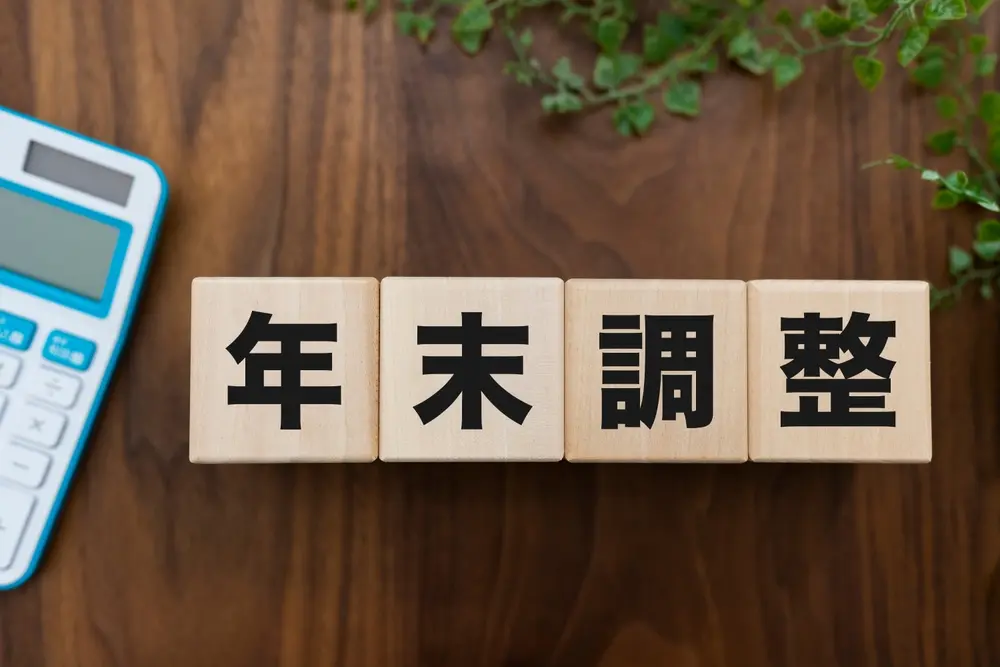


企業のみなさまへ
あなたもDXログにサービスを掲載しませんか?
あなたもDXログに
サービスを掲載しませんか?