IT導入補助金の不正受給は返還を要求される?事例や注意点を解説
補助金・助成金
2024.01.17
2024.01.17

DXを推進するためには、ITツールの導入が必要不可欠であり、IT導入補助金を活用するのがおすすめです。しかし、申請内容の不備や報告漏れ等があると、交付された補助金の返還を求められる場合があります。当記事では、IT導入補助金の不正受給と判断された場合の処分や補助金の不正受給の事例、IT導入補助金を申請・利用するときの注意点について解説します。
IT導入補助金を不正受給すると返還が必要
IT導入補助金とは、ITツールを導入して自社の生産性や売上を向上することを目的に、経費の一部を補助する制度のことです。
IT導入補助金の不正受給と判断された場合には、基本的には全額返還しなければなりません。また、公募要領の留意事項には下記の記載があります。
事業期間中および補助金交付後において、不正行為等、情報の漏洩等の疑いがあり、補助事業者として不適切であると事務局が判断した場合、事務局は、交付決定の取消し、補助金の返還命令等の処置を行う場合がある。
引用:公募要領 通常枠(A・B類型)|IT導入補助金2023
補助金の不正受給の事例
ここでは、補助金の不正受給の事例について詳しく紹介します。
日付の改ざん
IT導入補助金では、支給された補助金を事業に投資する実行期限として事業実施期間が設けられています。
その事業期間内の経費でなければ、補助対象経費にならないことがあります。そのため、補助対象期間外に実施した事業の発注書や契約書、納品書、領収書といった経費の証拠書類を、事業期間内の日付に改ざんし、補助対象経費と申請して補助金を不正受給とみなされた事例があります。
補助金の申請額の水増し
補助金の申請者(購入者)と協力者(販売者)が連携して、双方がメリットを得られるように補助金の申請額の水増しがおこなわれたケースもあります。
たとえば、20万円の補助対象経費に該当する製品があります。補助率が2分の1の場合、この製品を購入すると申請者は10万円の補助金の交付を受けられます。
しかし、販売者より30万円で購入するのであれば、50万円の領収書を交付するという条件を持ちかけられるとします。この場合、通常よりも販売者は10万円多く売上を出し、申請者は、本来の申請よりも15万円多く補助金を不正に受け取ることになります。
目的とは異なった補助金の使用
補助金の交付申請をおこなうときには、基本的に補助金の使用目的を伝える必要があります。また、その目的通りに補助事業がおこなわれたかを確認するために、事後報告が義務付けられています。
たとえば、補助金を「会社の業務で必要」という目的で申請して受け取ったけれど、実際は私用の目的で補助金を利用し、偽りの事後報告をおこなうと不正受給にあたります。
不正受給と判断された場合に受ける可能性のある処分
ここでは、IT導入補助金の不正受給と判断された場合に受ける可能性のある処分について詳しく紹介します。
補助金の返還に加えて加算金の支払が必要
IT導入補助金を不正受給すると、補助金の返還に加えて加算金を支払わなければならないこともあります。補助金適正化法第21条には、下記の記載があります。
各省各庁の長が返還を命じた補助金等又はこれに係る加算金若しくは延滞金は、国税滞納処分の例により、徴収することができる。
補助金の支給停止
IT導入補助金の公募要領にも記載があるように、不正受給をおこなうと交付決定の取り消しとなり、補助金の支給停止になる可能性があります。また、補助金適正化法第17条には、下記の記載があります。
各省各庁の長は、補助事業者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
引用:補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律|e-Gov
会社名が公表される
IT導入補助金の不正受給をおこなうと、経済産業省のページに会社名などの企業情報が公表される可能性もあります。掲載される情報は、下記の通りです。
- 法人名(法人番号)
- 住所
- 補助金等交付停止期間
- 指名停止期間
- 理由
会社の不正受給した情報が知れ渡ることで、社会的信用の低下につながり、今後の取引に影響を与える可能性があります。
補助金の再申請ができなくなる
IT導入補助金では、申請要件に下記が含まれます。
- 中小機構が実施する補助事業において、「虚偽の申請」や「利害関係者への不当な利益配賦」といった不正な行為を行っていない(加担していない)こと
- 今後も不正な行為を行わない(加担しない)こと
また、下記の事業者は、補助対象外になります。
経済産業省から補助金等指定停止措置または指名停止措置が講じられている事業者
引用:補助対象|IT導入補助金2023
このように、IT導入補助金に限らず、あらゆる補助金事業で不正をすると、以降補助金を受給できなくなる可能性があります。
罰金や懲役が科される
IT導入補助金の不正受給が悪質な場合には、罰金や懲役が科される恐れもあります。詐欺罪とみなされると、刑事訴追や刑事告訴につながる可能性もあります。補助金適正化法第29条には、下記の記載があります。
偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受け、又は間接補助金等の交付若しくは融通を受けた者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
引用:刑法|e-Gov
また、刑法第246条(詐欺罪)では、下記の記載があります。
引用:刑法|e-Gov
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する
引用:刑法|e-Gov
IT導入補助金を申請・利用する際の注意点
ここでは、IT導入補助金を申請・利用するときの注意点について詳しく紹介します。
申請内容に間違いがないかを確認する
IT導入補助金の交付申請をおこなう際には、申請マイページを利用し、事業者情報や財務情報、経営状況、ITツールの詳細など、さまざまな項目を入力します。
申請内容に間違いがあると、不採択になる可能性が高まります。採択されたとしても誤った内容で申請していることから、意図せず不正受給と判断され、補助金の返還や支給停止といった処分が下される恐れもあります。
信頼できるIT導入支援事業者を選定する
IT導入補助金の交付申請をおこなうには、導入するITツールを決めたり、申請手続きを進めたりするためにIT導入支援事業者を選定する必要があります。また、IT導入支援事業者は適切に補助金が交付がされるように、補助事業を管理・監督する役割を担います。
しかし、IT導入支援事業者によっては、自社の利益のためにITツールの購入費を通常よりも高く購入してもらう代わりに、偽りの領収書を発行して補助金の申請額を水増しするなどの不正をもちかけられる可能性がないとは言い切れません。そのため、経験や実績の豊富な信頼できるIT導入支援事業者を選定することが大切です。
交付決定の通知を受けてから補助事業を開始する
IT導入補助金では交付申請が完了した後、採択結果が通知される前にITツールの発注・契約・支払といった補助事業を開始してしまうと、補助金の交付を受けられません。必ず事務局から「交付決定」の連絡が届いたことを確認してから、補助事業を進めるようにしましょう。
申請内容と異なるITツールの導入や契約をおこなわない
IT導入補助金の交付申請では、IT導入支援事業者に導入するITツールの内容を記載してもらいます。申請者とIT導入支援事業者との間で認識の相違があると、申請した内容とは異なるITツールを導入・契約してしまう可能性があります。
思いがけない不正受給につながらないように、交付申請書を提出する前にきちんと内容を確認し、IT導入支援事業者の記述した内容に誤りがあれば訂正依頼を出しましょう。
経過報告を怠らない
IT導入補助金の申請フローでは、採択の結果を受けて補助事業を実施した後に事業実績報告を提出することで、補助金の交付手続きをおこなうことができます。
また、補助金の交付を受けた後は、事業実施効果報告(経過報告)をIT導入支援事業者の確認を受けたうえで、一定の期限までに提出する必要があります。この経過報告を怠った場合も補助要件を満たしていないとして、補助金の返還が求められる可能性もあるため注意が必要です。
不正受給にならないよう注意してIT導入補助金を活用しよう!
IT導入補助金の不正受給をおこなうと返還が求められます。場合によっては、加算金の支払や補助金の支給停止、会社名の公表、罰金・懲役といった処分が下る可能性もあります。補助金の不正受給は絶対におこなわないようにしましょう。
また、意図せず不正受給と判断されないためにも、申請内容をきちんと確認したり、信頼性の高いIT導入支援事業者を選定したりすることが大切です。













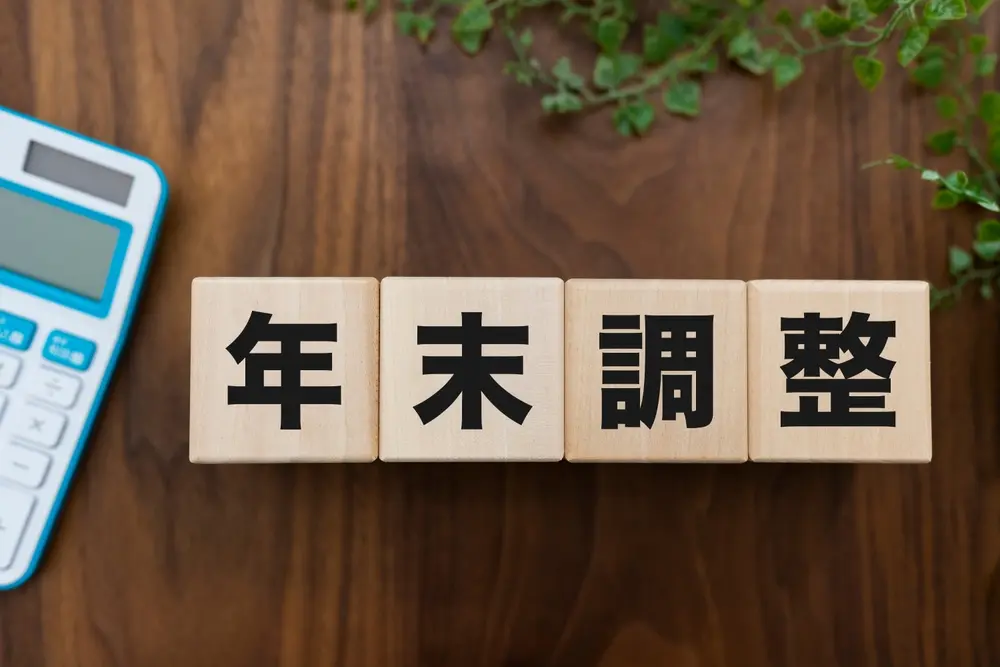


企業のみなさまへ
あなたもDXログにサービスを掲載しませんか?
あなたもDXログに
サービスを掲載しませんか?