給与計算ソフトのおすすめは?比較する際のポイントを詳しく紹介
給与計算ソフト
2023.10.23
2023.10.23

給与計算ソフトは種類が非常に多く、搭載されているシステムや価格もさまざまです。本記事では多くの給与計算ソフトのなかでも、クラウド型・パッケージ型・オンプレミス型から自社に最適な給与計算ソフトを選ぶ際のポイントを解説します。 給与計算ソフトの導入を検討中の企業様はぜひご覧ください。
給与計算ソフトの種類は主に3つ
給与計算ソフトには「クラウド型」「オンプレミス型」「インストール型」の3つと、「クラウド型+オンプレミス型」のような複合タイプがあります。給与計算ソフトを選ぶ前にそれぞれのタイプの特徴を知っておきましょう。
クラウド型給与計算ソフト
給与計算ソフトとして、主流になりつつあるのがクラウド型の給与計算ソフトです。クラウドから提供されるサービスで、ハードやパッケージソフトを購入する必要がなく、短期間&低コストでの導入ができます。
ソフトを購入する必要はありませんが、初期費用に加えて月額料金がかかるプランが一般的です。無料お試しサービスがついているソフトも多いため、そのようなサービスを活用しながら機能や操作画面を確認した上で導入をしましょう。
サポートが充実しているソフトも数多く提供されています。このようなソフトであれば、導入に不安がある場合や、使い方がわからない場合にオンラインなどで気軽に問い合わせることができます。
クラウド型給与計算ソフトは、スマホやタブレットなど、端末を選ばずに利用できる点が大きなメリットです。Web給与明細にも対応しているものが多く、これらを活用すれば従業員が各自Web上で給与明細を確認できるようになり印刷や配布コストも大きく減らせます。
また、法改正や税率改定へのシステム対応がオンラインで自動的におこなわれるため、更新忘れによるトラブルも起きません。一部の例外を除いて必要な変更は無料でアップデートされます。
【クラウド型がおすすめな企業】
- 社内のペーパーレス化を進めたい
- 複数の端末から給与計算ソフトにアクセスできる環境が欲しい
- 税制改正や法改正に自動で迅速に対応したい
- 従業員にITに慣れた若い世代が多い
インストール型給与計算ソフト
昔からあるタイプのインストール型給与計算ソフトは、ダウンロードやパッケージ購入によってソフトをパソコンにインストールして使用します。買い切りであるため、一度購入すれば月額料金はかかりません。
ネットショップや家電量販店で手軽に購入でき、基本的な計算をするだけであれば登録も必要ないため導入のハードルが低いといえます。
そのため、専門知識がない人や、パソコン操作に慣れていない人でも使いやすいものが多く、操作画面もわかりやすいものが目立ちます。 ネット回線がなくても使用できる点もインストール型の特徴です。
インストール型給与計算ソフトはサイバー攻撃による情報の流出が心配な場合や、ネット環境が整っていない場所での使用におすすめです。
しかし、税率や保険料率のアップデートが自動ではおこなわれず、アップデートが有料の場合もあるため、アップデートが必要となった際にどのような対応となるのかを購入前に確認しておきましょう。
【インストール型がおすすめな企業】
- 誰でも視覚的に分かりやすい簡単なソフトがいい
- できるだけコストを抑えて電子化を進めたい
- オフラインでも使える給与計算ソフトを選びたい
オンプレミス型給与計算ソフト
オンプレミス型給与計算ソフトはカスタマイズしたシステムを自社サーバーにインストールして使用します。自社に最適なシステム構築ができるため、細部まで調節できる点が魅力です。
システムの開発や設定に時間がかかり、導入する規模によって数百万円規模の費用がかかるもっとも高額なタイプです。そのため、中規模~超大型の企業向けのシステムといえるでしょう。
導入後はすべて自社で管理することになるため、月額費用は一切かかりません。
しかし、システムエンジニアをはじめとした専門知識がある人員で構成されたチームがないと、トラブルによって使用できなくなることや、データの消失・個人情報の外部流出などが懸念されます。
【オンプレミス型がおすすめな企業】
- 人材管理や給与計算などを一元化できるオリジナルシステムが欲しい
- 中~大規模の企業でシステム構築の予算を準備できる
- 社内にシステムエンジニアをはじめとした専門家がいる
給与計算ソフトは少人数向けなど対応範囲が異なる
給与計算ソフトは、従業員の給与額や各種手当、保険料などを自動で計算できるソフトで、給与計算にかかる業務の効率化し、ひいては人件費削減にもつながります。
ただし、どのソフトも似たり寄ったりというわけではありません。ソフトによって少人数向けなど対応できる範囲はさまざまで、年末調整にも対応しているものや、Web給与明細の発行に対応しているものもあります。
ここからは、自社に合った給与計算ソフトの選び方でお困りの方に向けて、給与計算ソフトのタイプを対応範囲別に紹介します。
給与計算特化タイプ
給与計算特化タイプは、その名の通り給与の自動計算や給与明細の発行といった限られた機能だけが搭載されているものです。利用できる機能が限定されている分、低コストでの導入が可能で、操作が簡単でわかりやすい点も大きな特徴といえます。
給与計算特化タイプの中には、Web明細を発行できたり、社会保険提出書類の作成をサポートする機能やマイナンバーを管理する機能といった、一部の労務管理に対応しているものもあります。
あくまでも目安ですが、従業員数が30人以下であればこちらのタイプでも十分に対応が可能といえるでしょう。
人事給与タイプ
人事給与タイプは、給与計算や管理だけではなく、様々な人事労務にも対応しているものです。労務管理システムや勤怠管理システムといったシリーズが展開されていたり、外部システムとの連携がしやすいものが多い点が大きな特徴です。
企業の体制や業務フローの変化、事業規模の拡大などの変化に応じて必要な機能が選択でき、段階的に業務のシステム化の拡張ができます。目安としては、従業員数が300名程度の場合は、こちらのタイプのソフトがおすすめです。
ERPタイプ
ERPタイプは、企業の主要な業務を統合的に管理し、効率化できるERP(基幹系情報システム)を活用したものです。人事業務に限らず、会計業務や販売業務などの領域にも対応しており、共通データを柔軟に活用できる点が特徴です。
大企業だけではなく中小企業に対応しており、目安としては従業員数が300名~1,000名を超える企業に向いているといえるでしょう。
給与計算ソフトを比較する際の7つのポイント
ここまでさまざまなタイプの給与計算ソフトを紹介してきました。 実際に導入する際には、以下の7つのポイントに注意して選ぶと自社に合ったソフトを見つけやすくなります。
自社の規模に合った給与計算ソフトを選ぶ
給与計算ソフトを選ぶ際は、自社の業務や従業員規模に合ったものを選びましょう。
小規模の企業であれば、高度な人員管理や賞与・昇給シミュレーションなどは使わないことが多く、ソフトの選び方によってはかえって余計なコストがかかってしまうこともあるからです。給与・賞与の計算や社会保険・年末調整など最低限の機能だけでも十分に活躍してくれるでしょう。
反対に、従業員数が多い企業では、給与計算ソフトによって大幅に業務の効率化が期待できます。登録したデータを給与計算以外にも使用することを考えて、必要なシステムが搭載されたソフトを選ぶことが大切です。
企業の規模が大きいほど複雑な人材管理が必要になるため、より多くの業務をカバーするソフトを選ぶことをおすすめします。
どんな機能が欲しいか明確にする
給与計算ソフトに求める機能を明確にしておくことも重要です。すでに税理士に年末調整や社会保険の計算を依頼している場合は給与計算だけをおこなうソフトで十分です。
すべてを自社でおこなう場合は、税金関連・保険関連の計算ができるソフトにしなければ厄介な計算や手作業が残ってしまいます。 賞与のシミュレーションや勤怠管理など、人員管理もまとめておこないたい場合は、それらに対応したシステムが必要です。
パッケージ型では対応しきれない場合は、オンプレミス型も検討して必要な機能を網羅できるようにしましょう。1つのソフトで管理できる情報が多いほど業務は効率化できます。
オンプレミス型には手が出せない場合は、オプションが豊富で選んで付け足せるプランがおすすめです。
社内に導入環境が整っているか確認する
給与計算ソフトにはクラウド型・オンプレミス型・インストール型があります。 クラウド型の給与計算ソフトはネットに繋がっていないと使用できません。そのため、トラブル時にも対応できる環境がないと、使いたいのに使えない状況に陥ります。
インストール型はネット環境がなくても使えるため、不安な場合はインストール型とクラウド型のハイブリッドタイプを選びましょう。
オンプレミス型は機能が豊富で、膨大なデータからの抽出作業もおこなえます。導入を検討する際は、パソコンのスペックがそれらの処理に対応できるかを確認しておくことも重要です。
実際に業務にあたる人と一緒に検討する
給与計算ソフトがどれほど多機能だとしても、それを扱える人材がいなければ無駄になってしまいます。経理や人事担当者など、給与計算ソフトをメインで操作する人が決まっている場合は、できるだけその人と一緒に選んだ方がスムーズです。
経営者の独断で決めてしまうと、現在のシステムに合わず導入後に混乱を招くことや、担当者のスキルとマッチせずに使えない可能性があります。 現在業務にあたっている人の意見があれば、どのようなシステムや操作性が適しているのか明確にわかるでしょう。
専門的に扱える人がいない場合は、操作が簡単な給与計算ソフトがおすすめです。シンプルな構成でも必要な機能はほとんど搭載されています。
オンプレミス型は自社サーバーにインストールされるため、ソフトを扱える人に加えてサーバーの管理者が必須です。システムエンジニアがいないとトラブル時の対応に費用と時間がかかってしまいます。導入する給与計算ソフトのレベルに合った担当者をつけられるかをよく検討しましょう。
どうしても使いたいソフトと担当者のスキルがマッチしない場合は、サポートが充実している会社の製品を選びましょう。出張デモやオンラインサポートがあれば、困ったときでも対応してもらえます。
体験版や無料期間があるソフトであれば、ぜひそれらも活用すると良いでしょう。
料金体系を確認する
多機能でさまざまな情報を登録・管理できる給与計算ソフトは魅力的です。そのようなソフトはほとんどの場合が高価ですが、前述したように使えなければ無駄になってしまいます。
はじめて給与計算ソフトを導入する場合は、まずは安価なものや無料体験がついているソフトを選びましょう。導入サポートが無償で付いてくるサービスもあります。
また、給与計算ソフトは料金体系も次のようにさまざまです。
- 1ライセンスで何名でも利用可能な定額制
- 利用者数に応じた従量課金制
- 一定の利用者数を超えるまで定額制(超えると従量課金制)
パートやアルバイト、インターンなど、従業員の出入りが多い場合は、利用者数に応じた従量課金制がおすすめです。
従業員数が少なければ無料で期間無制限に使えるサービスもおすすめです。 まずは「給与計算ソフトがどんなものか」「本当に自社に必要なのか」を理解してからじっくりと導入を検討しましょう。
システム連携が可能か確認する
給与計算は従業員の勤怠データをもとにおこなうため、勤怠システムとの連携が必要です。
すでに何らかの勤怠管理システムを利用している場合は、導入を検討している給与計算ソフトとの連携が可能かを確認しましょう。システム連携が可能であれば、給与計算業務が大幅に効率化されるため、人事担当者や経理担当者の負担が軽減されます。
なお、勤怠管理システムを利用しておらず、アナログな方法でおこなっている場合は、勤怠管理も可能な給与計算ソフトを選ぶことをおすすめします。
セキュリティやサポート体制を確認する
給与計算ソフトには人事に関する重要なデータも含まれているため、セキュリティ性の高いものであることが大前提です。パスワードによる保護ができることはもちろん、アクセスログが残るものなど、どのようなセキュリティ体制になっているかを確認しましょう。
また、基本的に有料の給与計算ソフトであれば電話やメールなどのサポートが付いているものの、サポート内容はソフトによってさまざまです。
たとえば、リモートアクセスや画面共有が可能であるか、専門のアドバイザーがいるかといった点も、給与計算ソフトをメインで使用する担当者のスキルに合わせて確認しておくことが大切です。
さらに、サポートに対応している時間や営業日についても確認しておくと安心でしょう。
給与計算ソフトは企業の規模と必要な機能で選ぶことが重要
業務の効率化と計算ミスの予防ができる給与計算ソフトは、導入すれば時間や人的コストを大幅に削減できます。それまで何日もかかっていた給与計算に関連する業務が数時間で終わるようになるでしょう。法改正や税率改定にも対応しているソフトを選べば、複雑な計算に悩むこともなくなるはずです。
ソフトによって搭載されているシステム・料金・操作画面などは大きく異なります。各ソフトの製品ページをよく確認し、問い合わせや無料体験をしっかりと活用してどのような特徴のソフトなのかを体感してみましょう。
「いろいろなシステムがある方が便利だから」という理由で、安直に高価なソフトを選ぶことは失敗や無駄なコストの発生を招きます。利用しないシステムが無駄になるだけでなく、操作画面が複雑になり業務の効率化が進まない可能性もあります。
まずは「給与計算ソフトで何がしたいのか」という目的を明確にし、従業員数に合った製品を選ぶようにしましょう。













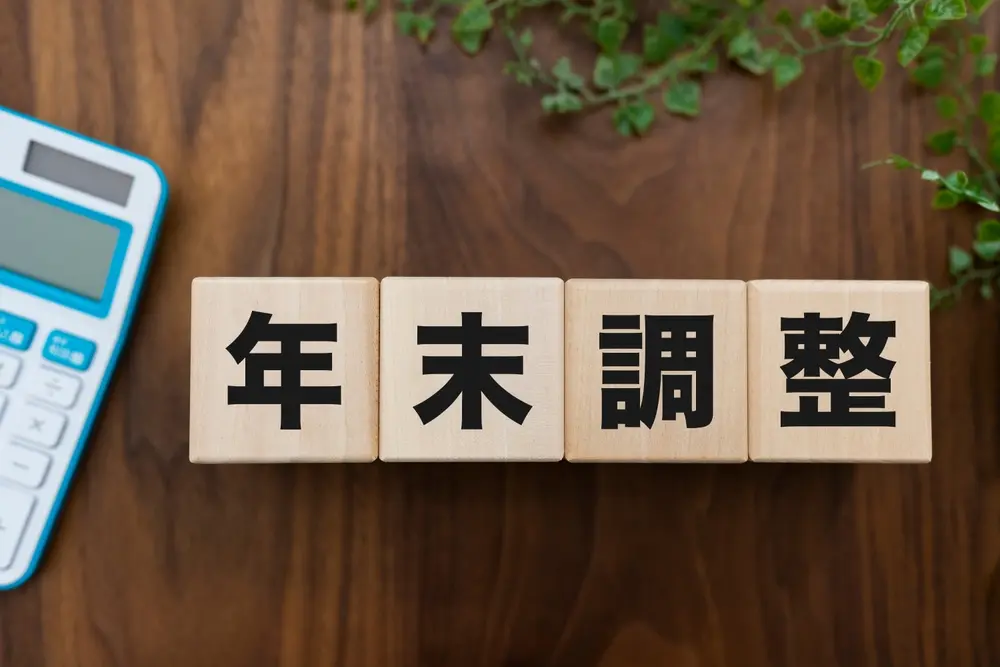


企業のみなさまへ
あなたもDXログにサービスを掲載しませんか?
あなたもDXログに
サービスを掲載しませんか?