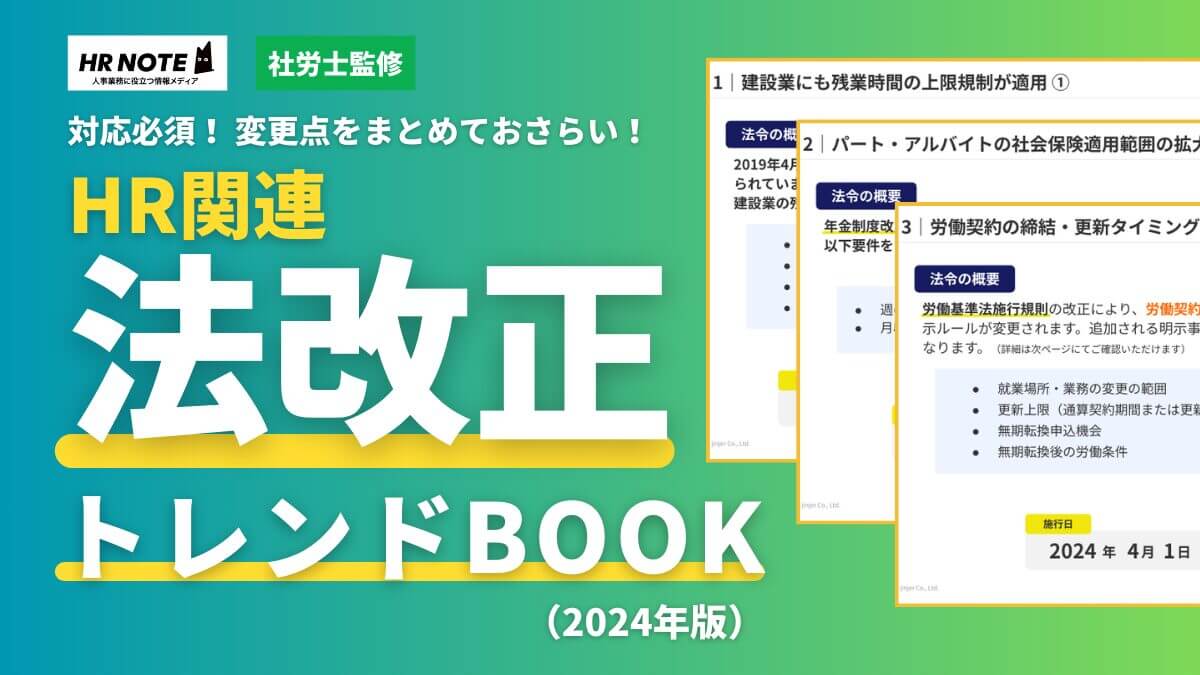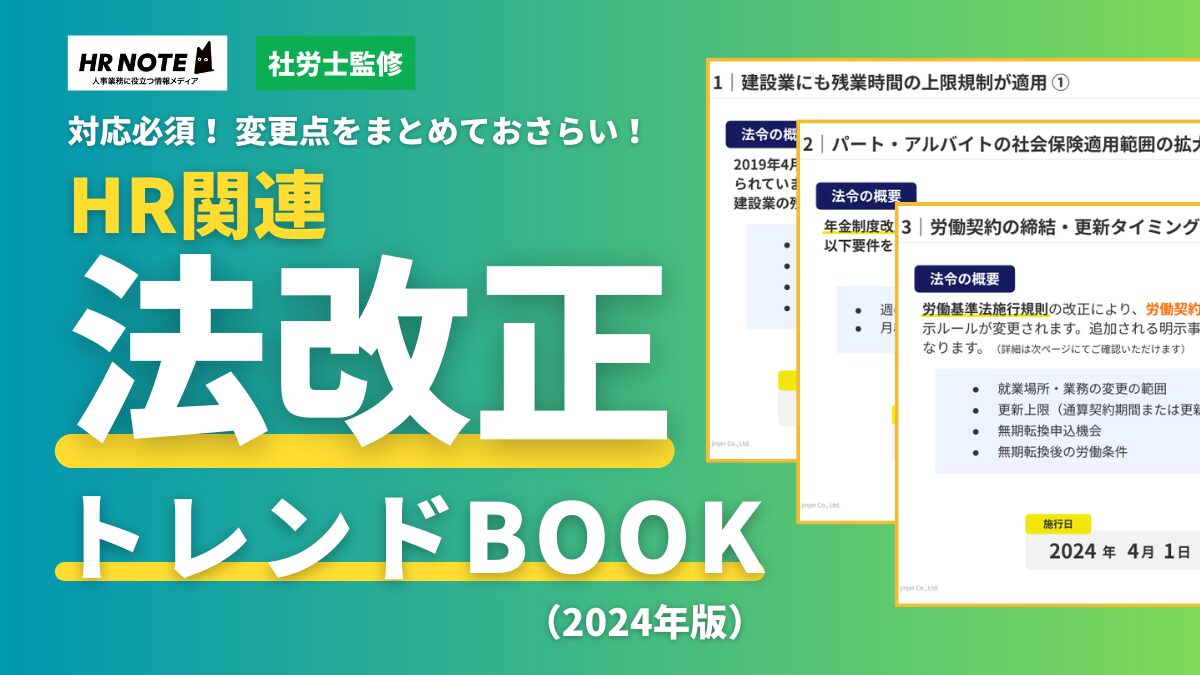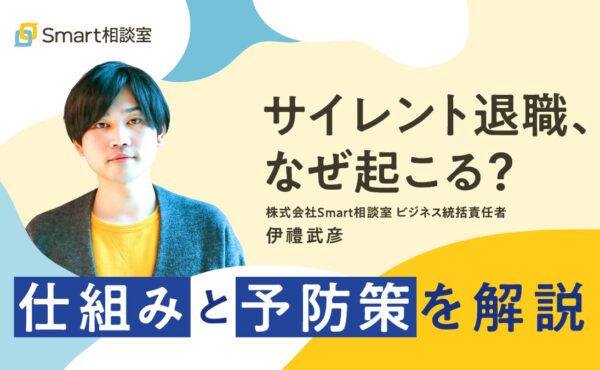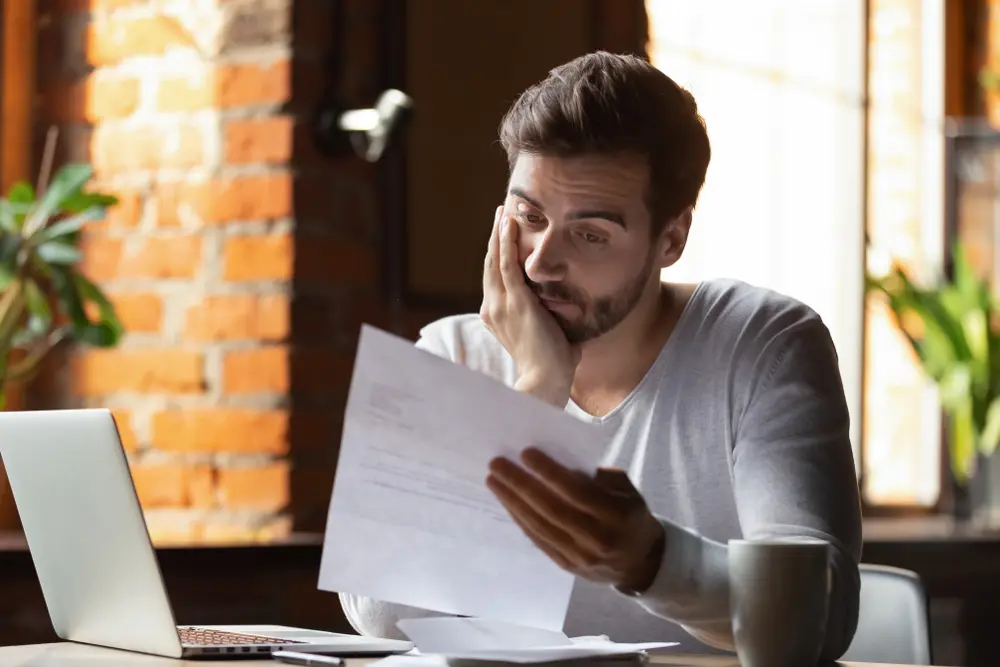
年末調整では、還付ではなく、追加徴収が生じるケースもあります。還付が生じる理由には、控除額が大きい場合などが挙げられます。しかし、追加徴収が発生する原因には、どのような場合があるのでしょうか。
また、所得欄がマイナス表記になり、追加徴収が発生した場合、申告の修正や確定申告、追加納税など必要な対応をとらなければなりません。本記事では追加徴収の原因や対策について詳しく解説していきます。
目次
【社労士監修】HR関連法改正トレンドBOOK 2024年版
2023年は一部企業を対象に人的資本開示が義務化されたほか、HR関連での法改正に動きが見られました。
2024年では新たな制度の適用や既存のルールの変更・拡大がおこなわれます。
人事担当者として知っておきたいHR関連の法改正に関する情報ですが、その範囲は幅広く、忙しい業務の中でなかなか網羅的に把握することは難しいのではないでしょうか。
- 忙しい中でも要点をまとめて情報収集をしたい
- 社労士が監修した正確な情報を知りたい
- HR関連の法改正を把握しておきたい
という方はぜひご確認ください!
1. 年末調整の追加徴収とは?
年末調整とは、給与所得者の毎月(毎日)の給料や賞与などから源泉徴収をした税額の合計と、その年の支払った給与に対して納めなければならない税額を比べて、その過不足金額を精算する手続きのことです。
年末調整の結果によっては、これまでに源泉徴収をおこなった税額の合計よりも、本来納めるべき税額のほうが大きいことがあります。この場合には、従業員にその差額を追加徴収します。これを年末調整の追加徴収といいます。
なお、その年の源泉徴収税額の合計よりも、本来納めるべき年税額のほうが小さい場合には、従業員にその差額を還付金として返金します。
年末調整で追加徴収が生じた場合には、追加徴収する金額を年末調整をおこなった月の給与から徴収します。通常は12月になることが多いですが、年末調整のスケジュールなどによっては、1月になることもあります。
1-1. 「追加徴収」と「追徴」「追徴課税」の違い
追加徴収と似た用語として、「追徴」や「追徴課税」が挙げられます。追徴とは「後から不足分を取り立てること」を意味し、追加徴収と同じ意味合いで用いられることが多いです。
一方、追徴課税とは、税務調査などで申告漏れや無申告が発覚した際に、本来の納税額との差額分を納めることをいいます。追徴課税の内容によっては罰則として、本来納めるべき税額に加えて、過少申告加算税や延滞税といった金額が加算される可能性もあります。
このように、追加徴収(追徴)と追徴課税は違った意味で用いられるので、正しく理解しておきましょう。
2. そもそも年末調整の目的とは?
従業員は毎月の給与や賞与などから所得税(復興特別所得税を含む)が差し引かれますが、この源泉徴収税額はあくまで概算であり、給与の変動などがあると、正しい年税額は変わってきます。
また、配偶者や控除対象親族の数が変化しても、その後の給与から修正されるだけで、それまでの源泉徴収税額は修正されないため、過不足金額が生じる原因になります。
さらに、地震保険料控除や生命保険料控除など、年末調整で受ける控除があることも過不足金額が発生する理由として挙げられます。
このように、大半の従業員は、その年の源泉徴収税額と納めるべき年税額において不一致が生じるため、年末調整により精算をおこなう必要があります。
年末調整を受けることで多くの従業員は、確定申告の手続きが不要になるため、税務関係の事務負担を軽減できます。
3. 年末調整の結果「追加
です。当記事では、年末調整とは何なのかについてわかりやすく解説します。年末調整の理由や対象者、スケジュール・流れなど、基本的徴収」となる原因・理由
ここでは、年末調整をおこなった結果、還付金が発生するのではなく、逆に追加納税分を支払う「追加徴収」となる場合について詳しく紹介します。
3-1. 賞与の金額が想定よりも多かった場合
賞与に対する源泉徴収税額は、「源泉徴収税額の算出率の表」をもとに算出率を求めてから計算します。
従業員の成果を賞与に反映させるなど、賞与額が大きく変化する会社では、想定しているよりも大きい賞与が支払われる従業員もいるかもしれません。
その場合には、その年の源泉徴収税額よりも、本来納めるべき年税額のほうが大きくなり、追加徴収となる可能性があります。
3-2. 年度途中で扶養人数が変更した場合
給与や賞与に対する源泉徴収税額は、源泉控除対象配偶者や控除対象扶養親族の扶養親族の数を反映した表をもとに計算されます。また、給与に対する源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与に変動がないものとして作成されています。
そのため、その年の途中で扶養人数が減った場合には、本来よりも多くの源泉徴収税額を納めなければならないのですが、変更後から修正されるだけで、遡って修正はおこなわれません。また、扶養人数が減ったことにより、年末調整で配偶者控除(配偶者特別控除)や、扶養控除などの控除を受けられなくなる可能性もあります。
このように、扶養人数が減ってしまうと、その年の源泉徴収税額の合計が本来納めるべき税額よりも小さくなってしまい、結果として、追加徴収となることがあります。
3-3. 給与の金額が大幅に変動した場合
給与に対する源泉徴収税額表は、先述したように、その年を通じて毎月の給与に変動がないことを前提に作成されています。そのため、1月から12月まで同様の給与を受け取ることを見込んで、源泉徴収税額は計算されています。
しかし、残業や休日出勤、人事異動などにより、給与に大幅な変動があると、その年の源泉徴収税額の合計と納めるべき年税額は一致しなくなります。
そのため、年末調整の結果で、場合によっては、追加徴収になる可能性があります。
3-4. その他控除額が減少した場合
その他さまざまな控除額が減ることによって、源泉徴収額よりも本来納めるべき税額のほうが大きくなり、追加徴収の原因になる可能性があります。たとえば、下記のケースが挙げられます。
- 障害の程度が軽くなり「障害者控除」が受けられなくなった
- 社会保険料の支払いが減り「社会保険料控除」の控除額が減った
- 「生命保険料控除」や「地震保険料控除」の控除を適用しなくなった
- iDeco(イデコ)の掛け金を減らしたため「小規模企業共済等掛金控除」の控除額が減った
このように、年末調整で受けられる控除の控除額が減少することで、その年の年税額は大きくなり、結果として追加徴収となる場合があります。
4. 給与明細の所得税が「マイナス」の場合は、追加徴収?
給与明細は会社によって様式が異なるため一概にはいえませんが、給与明細の「控除」欄でマイナスの数値がみられた場合、追加徴収された金額ではなく、還付された金額を示します。
たとえば、「控除」欄に「年末調整還付」「年調過不足税額」「過不足税額」といった項目があり、マイナスの数値で記載されていれば、還付を表します。
一方、同様の項目で「支給」欄でマイナスの数値がみられた場合や、「控除」欄の年末調整の項目でプラスの数値がみられた場合などは、追加徴収を意味します。
また、追加徴収の結果、支払う金額が多くなり、従業員からみると所得が減ったという意味でマイナスという言葉が使われることもあります。
5. 年末調整で追加徴収が発生した場合は繰延承認申請も検討
年末調整で追加徴収が発生した場合、年末調整をした月の給与から徴収します。一般的に12月におこなわれることが多いです。また、追加徴収しても不足額がある場合には、その後に支払う給与から順次徴収をすることになっています。
なお、年末調整をした月の給与から追加徴収をおこない、その月の税引手取給与(賞与があればその税引手取額を含む)が、その年の1月から年末調整をおこなった月の前月までの税引手取給与の平均月額の70%未満になる場合は、「年末調整による不足額徴収繰延承認申請書」を作成できます。(※1)
この申請書を、その年最後に給与などを受け取る前日までに、勤務先の所轄の税務署長に提出し、承認が得られれば、追加徴収を翌年の1月と2月に繰り延べることが可能です。
(※1)A2-10 年末調整による不足額徴収繰延の承認申請|国税庁
6. 年末調整の追加徴収の場合の納付時期はいつ?
源泉徴収税額は、原則として給与などを支払った翌月10日までに納める必要があります。(※2)
そのため、年末調整で追加徴収の場合の納付は、追加徴収をおこなった月の翌月10日までに納付することになります。たとえば、12月に追加徴収をおこなった場合には、翌年の1月10日までに納付しなければなりません。
ただし、納期の特例を受けている事業者や、年末調整による不足額徴収繰延の承認を受けている従業員については、一般的な納付方法とは異なる可能性もあるため、税務署や専門家などに相談してみるのがおすすめです。
(※2)No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁
7. 年末調整の追加徴収の計算方法
まずは、その年の毎月の給与や賞与などから源泉徴収をおこなった税額を合算して、合計金額を計算します。
次に、年末調整でその年の支払った給与を集計して、そこから給与所得控除を差し引き、課税所得金額を算出します。課税所得金額から、従業員が申告した所得控除(基礎控除や扶養控除など)額を差し引いて、残った課税所得金額に所得税率を掛けることで、暫定の所得税額を計算します。そして、暫定の所得税額から税額控除額を差し引いて、年税額を算出します。
これらの2つの税額を比較して、源泉徴収税額の合計よりも、年末調整で計算した年税額のほうが大きい場合には、その差額を従業員に追加徴収します。逆の場合は、その差額を従業員に還付します。
8. 年末調整での記載ミスは確定申告が必要になる可能性あり
ここでは、確定申告が必要になるケースを説明したうえで、確定申告での追加徴収について詳しく紹介します。
8-1. 確定申告が必要になるケース
まずは確定申告が必要になるケースを確認してみましょう。確定申告が必要になる主な場合は、下記の通りです。
- 年末調整の期限に間に合わなかった場合
- 年末調整の書類に記載ミスがあった場合
- 寄付金控除や医療費控除、雑損控除など年末調整で受けられない控除を適用する場合
- 住宅ローン控除(1年目)を適用する場合
- 副業やアルバイトを掛け持ちしているなど収入源が複数ある場合
- 年の途中に退職してその年のうちに再就職していない場合
- 年収が2,000万円を超える場合
- 災害減免法を適用する場合
たとえば、年末調整の書類に記載ミスがあったら、受けられるはずの控除が適用できず、控除額が減り追加徴収となるケースがあります。その場合は、確定申告をおこなうことで正しく申告し直すことが可能です。
なお、年末調整の期限(法定調書などの提出日でもあるその年の翌年の1月31日)、かつ勤務先が源泉徴収票を発行する前までであれば、勤務先で年末調整を訂正・修正することができるかもしれません。まずは年末調整で対応できるか勤め先に相談してみましょう。
8-2. 確定申告の場合でも追加徴収となる場合がある
確定申告をおこなったとしても、その年の納めるべき額よりも源泉徴収額のほうが少ない場合には、追加徴収となります。また、下記の場合には、追加徴収となる可能性が高いです。
- 給与所得以外の所得を申告した
- 年末調整で間違えて控除額が大きくなるように申告した
本業以外のアルバイトや副業などで得た所得については、源泉徴収されないケースもあります。そのため、確定申告する際に、控除額は変わらないが、所得が大きくなり、追加徴収となる可能性があります。
また、年末調整で間違えて控除額が大きくなるように申告した場合には、確定申告で申告し直す必要があります。所得は変わりませんが、控除額が小さくなるので、追加徴収となる場合があります。
8-3. 確定申告での追加納税の方法
年末調整では給与から天引きされる形で追加徴収がおこなわれるので、とくに追加徴収のための手続きは必要ありません。しかし、確定申告の場合は自分で追加納税をおこなう必要があります。納付期限は3月15日までです。この期限を過ぎると追徴課税される恐れがあるので注意が必要です。
確定申告書を作成する際に、追加徴収の必要な額が算出されます。その額を下記の方法で期限までに納付することで、課税関係は完結します。(※3)
- 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税をおこなう
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)を利用して納付する
- インターネットバンキングやATMを使用して納付する
- クレジットカードを活用して納付する
- スマホアプリ決済を利用して納付する
- コンビニエンスストアでQRコードを使用して納付する
- 現金で納付する
現金やATMで納付するよりは、クレジットカードやスマホアプリ決済などのキャッシュレスを利用したほうが、⾦融機関や税務署などに赴く必要がなく、場所を問わず納付手続きができるので、負担を軽減できます。
(※3)【税金の納付】|国税庁
9. 年末調整で追加徴収になった場合も適切に対応しよう!
年末調整により、その年の源泉徴収税額の合計よりも、本来納めるべき税額のほうが大きい場合は、追加徴収がおこなわれます。追加徴収が生じる原因・理由には、賞与が思っていたよりも大きかった場合や、年の途中で扶養人数が変わった場合などが挙げられます。
追加徴収が発生した場合は、年末調整をおこなった月の給与から徴収します。ただし、一定の要件を満たせば、追加徴収の時期を繰り延べることが可能です。
--------------------
▼無料ダウンロードはこちら▼
https://hrnote.jp/document/?did=148030