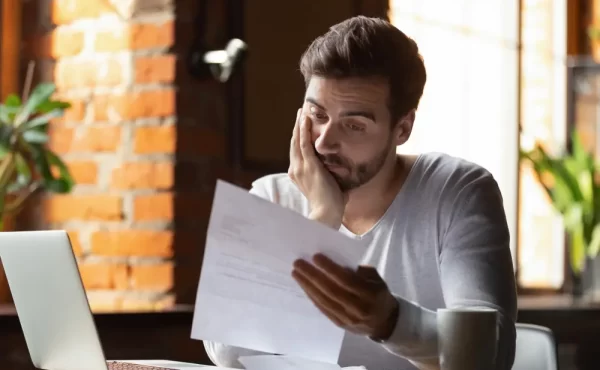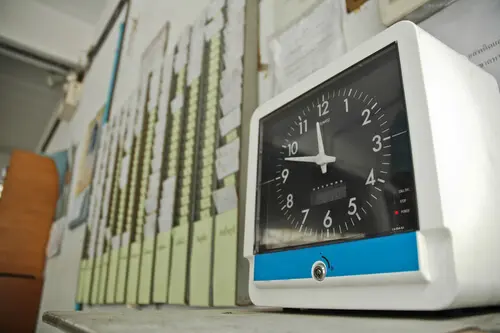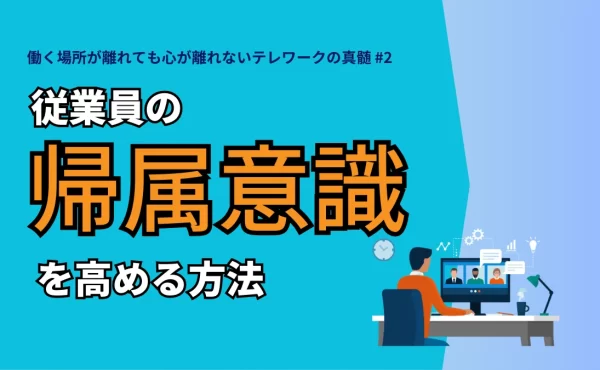従業員に夜勤の業務にあたらせる場合には、日勤の場合と同様に6時間を超える場合に45分、8時間を超える場合には1時間の休憩時間を取得させる必要があります。また、勤務体制によっては夜勤中の休憩時間に対しても賃金の支払いが必要になる場合があります。今回は、夜勤で休憩時間を取らせる場合のルールや注意点を解説します。
目次
1. 夜勤の場合の休憩時間のルール
夜勤の場合の休憩時間に関する規定について確認していきます。
夜勤の場合の休憩時間には、労働基準法第34条では「労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分間の休憩を、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩を労働時間の中で与えなければならない」と定めています。[注1]
労働基準法の中では、勤務する時間帯についての規定はないため、夜勤の場合でもこの要件に則り従業員に休憩を付与します。
1-1. 夜勤とは?何時から?
夜勤とは、深夜時間に業務をおこなうことです。労働基準法第61条では、深夜業について定義されており、深夜業の対象となる時間帯は午後10時から午前5時までです。そのため、 この時間帯に勤務する場合は、夜勤に該当することになります。
[注2]労働基準法|e-Gov法令検索
1-2. 夜勤時に休憩を取得させないことによる法的な問題
夜勤時でも、休憩に関しては基本的には日勤と同じ扱いとなるため、休憩を取得させないようなことがあれば法令違反(労働基準法第34条違反)となります。
そもそも休憩時間とは、労働者が業務を離れて自由にできる時間という定義があります。
待機時間や電話の待ち時間といった「手待ち時間」は休憩時間とはみなされないため、別途休憩を取得させる必要があります。
1-3. 夜勤での休憩時間の適用が除外される宿直勤務とは
夜勤時にも基本的に休憩時間の取得が必要となることは先に述べたとおりですが、一部の労働形態では、休憩時間の適用が除外される場合があります。
たとえば宿直や日直での勤務がこれに該当します。宿直勤務は労働基準法の定める断続勤務にあたります。
監視・断続的勤務や宿直勤務は、常態として身体または精神的緊張が少なく、休憩時間が少ない分、手待ち時間が実作業時間を上回るものが対象です。
そのため、監視・断続勤務や宿直勤務にあたっている従業員については、1日8時間を超えて勤務したり、休憩時間中に業務にあたったりした場合でも、休憩を取得させなくても法令違反にはなりません。
また、給与についても、最低賃金の減額の特例許可を受ければ、最低賃金より減額することが認められています。休憩や残業に関する規定は免除されますが、深夜労働の割増賃金は除外されていないため、深夜労働の割増賃金が発生した場合は適切に支払いましょう。
ただし、監視・断続勤務の勤務形態を適用するためには、労働基準監督署長の許可を得る必要があるため、注意が必要です。
これらは、労働基準法第41条や労働基準法施行規則第23条に規定されています。[注2][注3]
2. 夜勤の従業員に休憩を取得させるタイミング
夜勤時の休憩の取得タイミングについては、労働基準法に規定されていません。
そのため、基本的に労働時間内であれば、いつでも休憩を付与することが可能です。
労働基準法第34条で定められている「労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない」という点について守られていれば、特に問題はないとされています。
ただし、休憩時間は勤務時間の間で与える必要があり、勤務開始直前に与えたり、勤務終了直前に与えて従業員を早く上がらせたりするといった方法は認められないため注意しましょう。
3. 夜勤の休憩時間の賃金
夜勤休憩時間に対して賃金を支払う義務が発生するか否かについては、勤務の状況によって変わってきます。
以下、夜勤での休憩時間を「労働から開放された完全な休憩時間」「業務の発生を待機する手待ち時間」「仮眠時間」の3つのパターンに分けて解説します。
3-1. 完全な休憩時間であれば賃金の支払い義務はない
夜勤での休憩時間が、労働から開放された完全な休憩時間とみなされる場合は、賃金は発生しません。
また、管理者の指揮命令下にない時間については、給与の支払い義務はありません。
3-2. 業務の発生を待機する手待ち時間の場合には賃金が発生する
夜勤での休憩が、業務の発生を待つ「手待ち時間」に該当する場合には、いつ業務が発生するかわからない状態となります。
状況によっては、いつでも業務に復帰できるようにしておかなければならないため、休憩時間であっても賃金を支払う必要があります。
休憩時間が「手待ち時間」に該当するにもかかわらず、賃金の支払いが適切にされていない場合には、未払い賃金を請求される可能性もあるので注意しましょう。
3-3. 夜勤中の仮眠時間の取り扱いは勤務体制で異なる
夜勤に仮眠時間を設ける場合もありますが、仮眠中の賃金形態は企業がとる仮眠時の勤務体制により大きく異なります。
たとえば、仮眠時間をとることはできるものの、業務が発生したら即対応しなければならないという場合には、仮眠時間は先に述べた「手待ち時間」に該当するため、労働時間として取り扱われます。
しかし、仮眠時間を取る場合でも、他の従業員が対応すれば問題ないというような交代制をとっているのであれば、労働から開放された時間として完全な休憩時間とみることができます。
夜勤休憩時間における仮眠時間を給与支払いの対象としないのであれば、このように仮眠をとっている従業員が業務にあたらなくても良い体制を整えることが重要となります。
4. 夜勤において休憩時間を確保するためにすべきこと
夜勤において休憩時間を確保するためには、企業側として次の2つの努力をする必要があります。
4-1. 夜勤での休憩時間のルールを設定する
日勤の場合と比較し、夜勤の場合には休憩時間のルールが明確化されていないケースが多いです。
そのため、休憩時間を取り忘れたり、管理者が休憩時間をとらせないまま業務にあたらせてしまったりということもありえます。
そのようなことがないよう、夜勤の休憩時間については従業員ごとの休憩時間を定めたり、勤務時間に対する適切な休憩時間を確認したうえでシフトの管理をおこなったりすることが大切です。
4-2. 夜勤専門の補助要員を確保する
業種によっては、人手不足のために夜勤でなかなか休憩時間を取ることができないという現状があります。
そのような場合には、夜勤専門の補助要員を確保するといった工夫をするとよいでしょう。
一部の業務を夜勤専門の補助要員に任せることにより、従業員がスムーズに休憩時間を取得しやすくなります。
4-3. 仮眠スペースを用意する
夜勤労働者は生活リズムが不規則になり、健康の悪化を招きやすいです。また、集中力が低下することで、業務中に甚大なミスをしてしまい、企業が大きな損害を被る恐れもあります。
そのため、夜勤の休憩時間の過ごし方として、夜勤中の疲労感を軽減して仕事に集中できるよう、仮眠をとることが推奨されます。夜勤従事者が休憩時間に仮眠を取りやすくするために、仮眠スペースを用意するのも一つの手です。
5. 夜勤の労働の注意点や休日や休暇のルール
ここまで、夜勤の休憩時間の扱いについて解説してきましたが、夜勤には休憩時間以外にも守る必要がある規定が複数あります。
そのほかの注意事項についても確認しておきましょう。
5-1. 夜勤は割増賃金の支払が必要
夜勤の勤務時間のうち、労働基準法の深夜業にあたる22時から翌5時の時間に対しては、賃金を規定の割増率で割増して支払う必要があります。
深夜労働に対する割増率は基礎賃金の25%です。下記の式で算出し、適切な賃金を従業員に支払いましょう。
| 深夜労働の割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 深夜労働の合計時間数 × 深夜労働の割増率(1.25) |
※月給制の場合、1時間あたりの基礎賃金の算出には注意が必要です。以下の式で算出しましょう。
| 1時間あたりの基礎賃金=月給 ÷ {(365-年間休日)×1日の所定労働時間÷12カ月} |
5-2. 夜勤明けの休日の取らせ方
労働基準法では、休日は暦日(0時から午後24時までの継続した24時間)で付与しなければならないとされています。
そのため、夜勤明けの日を休日とみなすことはできません。
たとえば、月曜日の21時から勤務を開始し、火曜日の5時に勤務を終えた従業員であれば、火曜日を休みとすることはできないので、水曜日の1日を休みとして付与します。
有給休暇についても同様の規定があるため、夜勤明けの休日の付与には注意しましょう。
5-3. 夜勤と日勤の連続勤務
夜勤からの日勤や日勤からの夜勤は違法にはなりません。
法定労働時間を超過した勤務時間に対する時間外労働の割増賃金等はしっかりと支払いましょう。
また、労働基準法では1週間に1日または、4週間を通して4日以上の休日を与えなければならないと定められています。これを法定休日とよびます。
この法定休日の規定に従えば、最大で24日間連続で勤務させることができます。
ただし、労働契約法において企業は労働者が安全で健康に労働できるように配慮しなければならないという安全配慮義務が定められているため、従業員の負担が大きくならないよう注意しましょう。
5-4. 夜勤労働者は年に2回の健康診断が必要
夜勤労働者は、労働安全衛生規則第45条より、「特定業務従事者」に該当するため、年に2回の健康診断が必要です。[注4]
正しい時期に健康診断を受けさせないと、従業員の健康悪化リスクを高めたり、労働安全衛生法違反で罰則を受けたりする恐れがあるので、適切なタイミングで健康診断を受けてもらうように社内ルールを策定することが大切です。[注5]
[注4]労働安全衛生規則法|e-Gov法令検索
[注5]労働安全衛生法|e-Gov法令検索
5-5. 「残業時間の上限規制」にも注意が必要
2019年4月より働き方改革関連法が施行されており、法律で残業時間の上限が定められるようになっています。[注6]夜勤労働者は、手待ち時間なのか、休憩時間なのかなど、正しく労働時間を計算するのが難しい場合があります。
残業時間の上限を超えて働かせてしまったというケースがないよう、リアルタイムで正しく労働状況を管理することが大切です。従業員の労働状況の管理に課題を感じている場合、勤怠管理方法を見直し、自社のニーズにあった勤怠管理システムの導入を検討してみるのもおすすめです。
6. 夜勤での休憩時間を確保して従業員が働きやすい環境を整えよう
今回は夜勤における休憩時間取得の際のルールや夜勤時における休憩時間取得のタイミング、また夜勤での休憩時間における給与の取り扱いについて紹介しました。
従業員が働きやすい環境を整えるためにも、夜勤での休憩時間についてはルール化し「労働から開放される時間」については、きちんと休憩を付与する必要があります。
休憩時間であるにもかかわらず、業務にあたらせた場合には、賃金が発生するため注意が必要です。
特に従業員の負担が大きくなりがちな夜勤では、事故やミス防止のためにも十分な休憩時間を設けなければなりません。
夜勤での休憩時間を確保するためにも、現状における夜勤での休憩時間のルール見直しや夜勤での補助要員の確保などを検討してみるとよいでしょう。また、従業員の労働状況を適切に管理できるよう、勤怠管理システムの導入を検討してみるのもおすすめです。